
「味噌づくりって自由研究になる?」「子どもでもできるの?」
そんな悩みに寄り添いながら、家庭でできる味噌づくり体験をわかりやすく紹介します。
本記事では、発酵のしくみや観察ポイント、顕微鏡での微生物チェック、さらには保育園や小学校での実践事例まで、幅広く取り上げています。
味噌を通じて“科学・食・文化”を一度に学べる内容なので、自由研究や親子の学びにぴったり。
初めての方でも安心して取り組めるよう、キットや書籍もご紹介しています。
味噌は“学びの宝庫”!自由研究や家庭教育にぴったり

味噌と発酵が教えてくれること
日本の食卓に欠かせない味噌。実はこの味噌、ただの調味料ではなく、子どもたちの「学び」を深める題材としてもとても優れていることをご存知でしょうか?
味噌の魅力のひとつは、発酵という目に見えない不思議な現象を身近に体験できることです。味噌づくりでは、こうじ菌や酵母菌、乳酸菌といった微生物たちが、大豆と塩と米(または麦)をじっくり変化させ、香り高く旨みのある発酵食品へと変えていきます。
このプロセスを観察することで、子どもは次のような学びの体験を得られます。
-
微生物の働きによる分解と変化
-
時間の経過とともに変わる色・香り・質感の違い
-
「生き物が関わる食品づくり」という食育視点
特に、家庭で味噌を仕込んだ後の1週間〜1ヶ月ほどの観察期間は、自由研究として最適です。味噌の色が濃くなる、香りが変わる、小さな気泡が出る…こうした変化を記録するだけでも、観察力や記述力がぐんと育ちます。
また、味噌づくりは「待つこと」も含めた体験。発酵の進行には時間が必要で、子どもたちはその過程で忍耐力や自然のリズムへの理解も育んでいきます。
なぜ子どもの自由研究に「味噌」が向いているのか?
毎年夏休みに悩むのが、自由研究のテーマ選び。そんな時こそ「味噌」が頼れる存在です。なぜなら、味噌には以下のような「研究しやすさ」と「教育的価値」があるからです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 準備が簡単 | 大豆・米こうじ・塩があればOK。キットも充実 |
| 安全で親子で取り組める | 火や薬品を使わず安心 |
| 観察テーマが豊富 | 色、香り、カビ、微生物…興味が尽きない |
| 記録・まとめがしやすい | 写真や日記形式で記録可能 |
さらに、こうじ菌や酵母といった微生物の存在は、近年「腸内環境」や「免疫力」といった健康面でも注目されている分野です。小学校中学年以上であれば、こうじ菌の働きを顕微鏡で観察したり、カビが発生しやすい場所としにくい場所を比較するなど、実験テーマとしても発展させやすいです。
「味噌の表面にカビが出たけど、これは失敗?」といった疑問も、自由研究の“答えを探す力”を育てるチャンスです。調べ、考え、工夫する──それこそが自由研究の本質。味噌づくりはそのすべてを含んでいます。
また、家庭で味噌を仕込むことで、「食は自然と人が育むもの」という気づきが芽生えます。大豆という“タネ”が、時間と菌の力で発酵し、家族の食卓へとつながる…その過程は、SDGsやローカルフード教育の一環としても非常に有意義です。
【まとめ】
味噌づくりは、子どもにとってただの工作でも調理でもなく、「食べられる自由研究」ともいえる貴重な体験です。
科学、食文化、自然との共生、観察と記録。これらをバランスよく学べるのが、味噌のすごさ。自由研究で悩んだら、ぜひ一度「親子で味噌を仕込んでみる」ことからはじめてみてください。
家庭でできる!味噌づくり体験のすすめ
味噌づくりは、子どもにとって「科学」「食育」「文化」のすべてを学べる体験です。自宅のキッチンで気軽に始められるうえ、自由研究の題材としても注目されています。ここでは、家庭で無理なく挑戦できる味噌づくりの方法と、親子で楽しむポイントをご紹介します。

準備するもの(材料・道具)
味噌づくりに必要な材料は意外とシンプルです。最近では、初心者でも手軽に始められる「味噌づくりキット」も市販されていますが、自分で揃える場合は以下を参考にしてください。
| 材料 | 目安(完成約1kg分) |
|---|---|
| 大豆 | 約250g |
| 米こうじ(または麦こうじ) | 約250g |
| 塩 | 約100g |
| 保存容器(タッパーやホーロー容器など) | 1L以上 |
| ラップ・重し(塩や袋詰めの重石で代用可) | 適量 |
材料はすべてスーパーやネット通販で入手可能です。こうじは「生こうじ」か「乾燥こうじ」のどちらでもOKですが、発酵が進みやすい生こうじが初心者にはおすすめです。
作り方をステップで紹介|親子で一緒に楽しむコツ
子どもと一緒に作るなら、工程を「遊び」や「観察」の視点で楽しむのがコツです。
【味噌づくりの基本ステップ】
-
大豆を一晩水に浸ける(8~12時間)
-
大豆をやわらかくなるまで煮る(圧力鍋なら短縮可)
-
煮た大豆を潰す(すりこぎ・マッシャーで)
-
米こうじと塩を混ぜ、つぶした大豆と合わせてよく混ぜる
-
空気を抜きながら「味噌玉」にして容器に詰める
-
表面をラップで覆い、重しをして冷暗所で保管
煮る・潰す・混ぜるといった工程は、小さな子どもでも手を動かしながら楽しめます。汚れてもOKな服装で、あえて「手を使って感じる」ことを大切にすると、記憶に残る学びの体験になります。
ポイントは「味噌玉」!子どもが喜ぶ工程とは?
味噌づくりの工程の中で、子どもが特に盛り上がるのが「味噌玉づくり」です。
味噌玉とは、空気を抜くためにこぶし大に丸めた味噌のこと。混ぜ終わった味噌をハンバーグのように空気を抜きながら丸め、容器に「ポン!」と投げ入れるこの工程は、まさに遊びの延長。自然と笑顔がこぼれます。
このとき、「何個できるか数えてみよう」「大小さまざまな玉を作ってみよう」といったミニゲーム感覚を取り入れると、さらに楽しくなります。
また、空気に触れた部分からカビが出やすいため、表面はしっかりラップで覆い、重しで密封することが発酵成功のポイントです。
【まとめ】
家庭での味噌づくりは、「食べる」だけでなく「観察する・学ぶ・作る」を一度に体験できる最高の自由研究素材です。
必要な道具や材料はシンプルで、工程も子どもと一緒に楽しめる内容ばかり。特に「味噌玉」の工程は、五感をフルに使った“発酵教育”の入り口となるでしょう。
数ヶ月後に完成する味噌は、子どもの手で生まれた「発酵の結晶」。それを食卓で味わうとき、きっと大きな達成感が親子の心を満たしてくれます。
自由研究ネタに最適!味噌の“発酵観察”アイデア
味噌づくりは、仕込んで終わりではありません。そこから始まる発酵の変化を観察する時間こそ、自由研究にぴったりな学びの場になります。ここでは、子どもにもわかりやすい発酵のしくみや、日々の変化をどう記録してまとめるかなど、観察のコツをご紹介します。
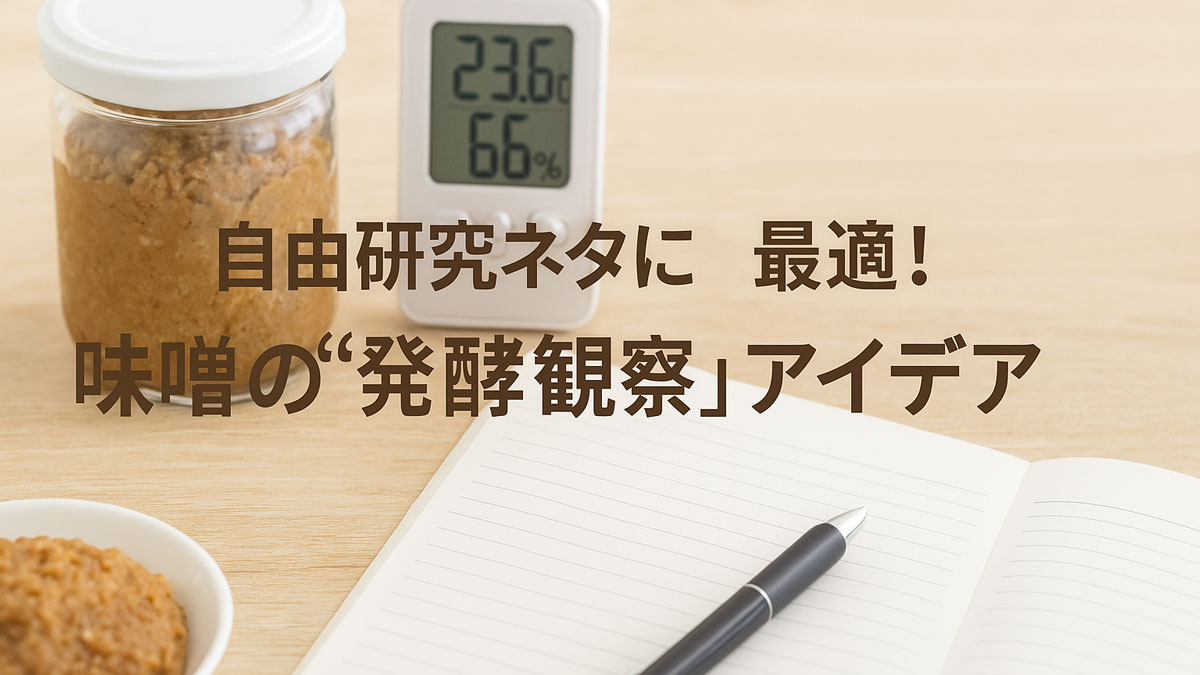
発酵のしくみを子ども向けにわかりやすく解説
発酵とは、「微生物の働きによって食べ物の性質が変化すること」。味噌の場合は、主にこうじ菌・酵母・乳酸菌の3つの微生物が関わっています。
-
こうじ菌:でんぷんやたんぱく質を分解して、甘みや旨味を生み出す
-
酵母:アルコールや香り成分を作り出す
-
乳酸菌:酸味を生み出し、味噌の保存性を高める
こうした微生物たちは、目には見えないけれど味噌の中で活動し続けています。その結果、大豆の色が濃くなったり、香りが変化したりするのです。
子どもには「微生物は小さな生き物で、食べ物をおいしくしてくれる“見えない料理人”」と説明すると、ぐっとイメージしやすくなります。
微生物が働く条件(温度・湿度・酸素など)も伝えると、観察結果に対する“なぜ?”が深まり、探究心につながります。
カビや色の変化を観察して記録しよう
味噌を仕込んだあとは、室温や保存環境によって徐々に変化していきます。観察は毎日でなくてもOK。週に1回程度、写真とともに記録をとるのがおすすめです。
観察できるポイント例:
-
色の変化(最初は白っぽい→徐々に茶色に)
-
表面に出るカビの色・量
-
香りの変化(塩っぽい香り→甘みやコクが出てくる)
-
気泡の発生(微生物の活動でガスが出ることも)
特にカビについては、子どもにとって印象的なポイント。白カビは正常な発酵の一部ですが、青や黒、ピンクなどのカビが出た場合は注意が必要です。「良いカビ」と「悪いカビ」の見分け方を親子で調べるのも、研究の幅が広がります。
また、発酵の進行に差が出るように、「冷蔵庫保存」「室温保存」で分けて比較するのもおすすめです。
自由研究レポートに役立つ「観察項目」例
自由研究としてまとめる際は、以下のような項目を観察・記録していくと、構成がしっかりしたレポートになります。
| 観察項目 | 内容例 |
|---|---|
| 日付 | 観察日を記録(例:7月1日) |
| 色の変化 | 白っぽい→茶色に変化 |
| 香りの印象 | 甘くなってきた/アルコールのような香り |
| カビの有無 | 白カビあり/青カビなし/カビなし |
| 気づいたこと | 少し汁が出てきた、フタの内側に水滴がついていたなど |
可能であれば、写真を毎回撮っておくと、視覚的に変化をまとめやすくなります。スマートフォンで撮影し、プリントしてレポートに貼り付けると、見栄えも良くなります。
【まとめ】
味噌の発酵は、毎日少しずつ変わっていく“生きた変化”を感じられる絶好の学びの素材です。観察するだけでなく、「なぜこうなったのか?」を考えることで、科学的思考力が自然と身につきます。
手軽にできるけれど、奥が深い味噌の発酵観察。今年の自由研究は、ぜひ「おいしく育つ発酵のチカラ」に注目してみませんか?
顕微鏡で見てみよう!味噌の微生物と仲良くなる学び
味噌の発酵を支えているのは、目には見えないけれど大活躍している微生物たち。この微生物の世界をのぞいてみることは、子どもたちにとってまさに「未知との出会い」になります。自由研究としてもインパクトがあり、観察→記録→考察の一連の流れを自然に体験できます。
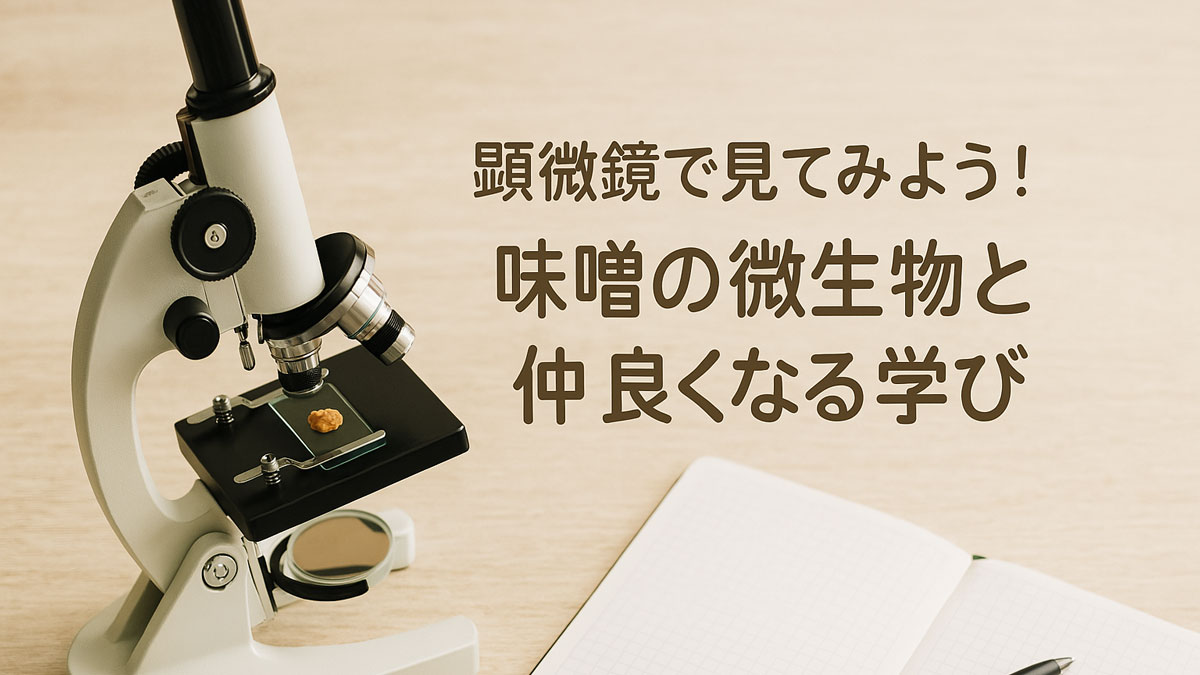
味噌にいる“こうじ菌”や“酵母”を観察してみよう
味噌の発酵に関わる微生物には主に以下のような種類があります。
| 微生物の名前 | はたらき | 観察ポイント |
|---|---|---|
| こうじ菌(Aspergillus oryzae) | デンプンやタンパク質を分解し、旨味を作る | 白く細い糸状の菌糸。胞子の構造が見えることも |
| 酵母(Saccharomyces属) | アルコールや香り成分をつくる | 丸くて小さい細胞が動く様子も観察可能 |
| 乳酸菌 | 酸味を生み出し保存性を高める | ごく小さな粒状。染色すると見つけやすい |
顕微鏡で観察するには、発酵中の味噌をほんの少し水で溶かして、スライドガラスにのせてカバーガラスで押さえるのが基本です。
100倍程度の顕微鏡でも、こうじ菌の菌糸や酵母の丸い細胞が観察できることがあります。染色液(メチレンブルーなど)があると、よりはっきり見えますが、なくても形や動きは確認できます。
「目に見えない世界に、こんなにたくさんの“いのち”がいるんだ!」という気づきは、子どもにとって非常に大きな学びになります。
観察結果をまとめるコツと子ども向けの解説例
観察結果を自由研究としてまとめる際は、「難しい言葉を使いすぎない」「見たままを素直に表現する」のがポイントです。子どもの言葉で表現すること自体が、研究の一部だからです。
まとめのステップ例:
-
観察した日付・倍率・使用した顕微鏡の種類
-
見えた微生物の形・動き・色などの感想
-
図や写真を添える
-
わかったこと・気づいたことを文章にする
【観察まとめの例:小学生向け記述】
顕微鏡で味噌を見たら、白くて細い毛みたいなものがたくさん見えました。これがこうじ菌だと知っておどろきました。最初はただの茶色い味噌に見えたけれど、中にはたくさんの生き物がいて、味をつくってくれていることがわかりました。
観察ができたら、「こうじ菌の住んでいる味噌の中は、どうして生きやすいのか?」など、ひとつ深い問いを立てて調べるのもおすすめです。たとえば、「塩分が高いのに菌が生きているのはなぜ?」「温度が高すぎるとどうなる?」といった疑問は、理科・科学の探究心に直結します。
また、観察後に「味噌を使った料理を家族にふるまってみる」という実践も合わせると、観察→活用→共有という、学びの循環が生まれます。
【まとめ】
顕微鏡で味噌を観察する体験は、目には見えないけれど確かに存在する“微生物の世界”と出会う学びです。こうした体験は、理科や生物に興味を持つきっかけとなり、自由研究としても高い評価を得やすいテーマです。
親子で「見て」「感じて」「記録する」。そんな小さな実験の中に、大きな学びが詰まっています。今年の自由研究は、ぜひ“発酵の小さな仲間たち”との出会いからスタートしてみませんか?
味噌を通じて育む「食育」|親子で学ぶ発酵文化
日々の食事に欠かせない味噌は、単なる調味料にとどまりません。子どもたちの「食べる力」を育てる食育のツールとしても、大きな可能性を秘めています。ここでは、日本の伝統食としての味噌文化をどう子どもに伝えるか、また実際に保育園や学校で活用されている事例を紹介します。

日本の伝統と味噌文化を伝えるチャンスに
味噌の起源は奈良時代までさかのぼり、長い年月をかけて日本の発酵文化の中心として受け継がれてきました。毎日の味噌汁だけでなく、味噌漬けや味噌煮など、地域や家庭によって使い方や味もさまざま。そんな“日常の中にある伝統”こそ、子どもに伝える価値のある学びです。
特に、親子で味噌を仕込む体験は、「食べ物がどうやってできるのか」を知る第一歩となります。ただ買ってくるだけでは見えなかった、時間や手間、自然の働きへの理解が深まるのです。
「昔はどの家でも味噌を仕込んでいたんだよ」といった話を添えるだけでも、食卓が学びの場に変わります。
また、季節と連動して仕込む味噌は、日本の四季を感じるきっかけにもなります。たとえば「寒仕込み」は冬の風物詩であり、春~夏に発酵が進んで味噌の味が深まっていく様子は、まさに時間が育てる味。こうした感覚は、デジタル世代の子どもにとって貴重な体験となるでしょう。
保育園・小学校での取り入れ方の実例紹介
味噌づくりや発酵観察は、すでに多くの教育現場で導入が進んでいます。ここでは実際の取り組み例をご紹介します。
【事例①】保育園での味噌玉づくり(5歳児クラス)
ある東京都内の保育園では、毎年冬に「味噌玉づくり」を実施。あらかじめ煮た大豆と米こうじ・塩を保育士が用意し、子どもたちは自分の手で“味噌玉”を成形。容器に詰めて持ち帰り、家庭で半年後の味見を楽しむそうです。
この取り組みは、“自分の手で作ったものを食べる”という経験を通じて、食べ物への関心と感謝の気持ちを育てていると評価されています。
【事例②】小学校の総合学習での発酵観察(3~4年生)
ある地方の公立小学校では、「地元の伝統食品を学ぼう」というテーマのもと、地元の味噌屋さんと連携して味噌仕込み&発酵観察を実施。観察ノートをつけたり、顕微鏡でこうじ菌を見たりすることで、理科・社会・家庭科がつながる学びとなっています。
さらに、地域との関わりや伝統の継承という視点でも評価され、保護者にも人気のある活動になっているとのことです。
【まとめ】
味噌を通じて学べることは、「栄養」や「料理」にとどまりません。発酵の不思議、季節との関わり、日本の文化、そして命を支える食への感謝——そのすべてを1つの味噌づくり体験が教えてくれます。
家庭でも学校でも、味噌は“生きた教材”。忙しい日々の中でも、少し立ち止まり、子どもと一緒に仕込み、変化を観察し、食べる。その一連の流れが、かけがえのない食育になります。
今年はぜひ、「味噌」を通じて親子で一緒に、食の未来を学んでみませんか?
【まとめ】味噌づくりは学びとおいしさが詰まった体験
味噌づくりは、ただの手作り体験ではありません。科学的な知識、食の大切さ、日本の伝統文化への理解と、子どもの成長に役立つ学びがたっぷり詰まっています。ここまで紹介してきた内容をふまえ、最後に「親子で味噌づくりを取り入れるメリット」と「おすすめのキットやツール」をご紹介します。
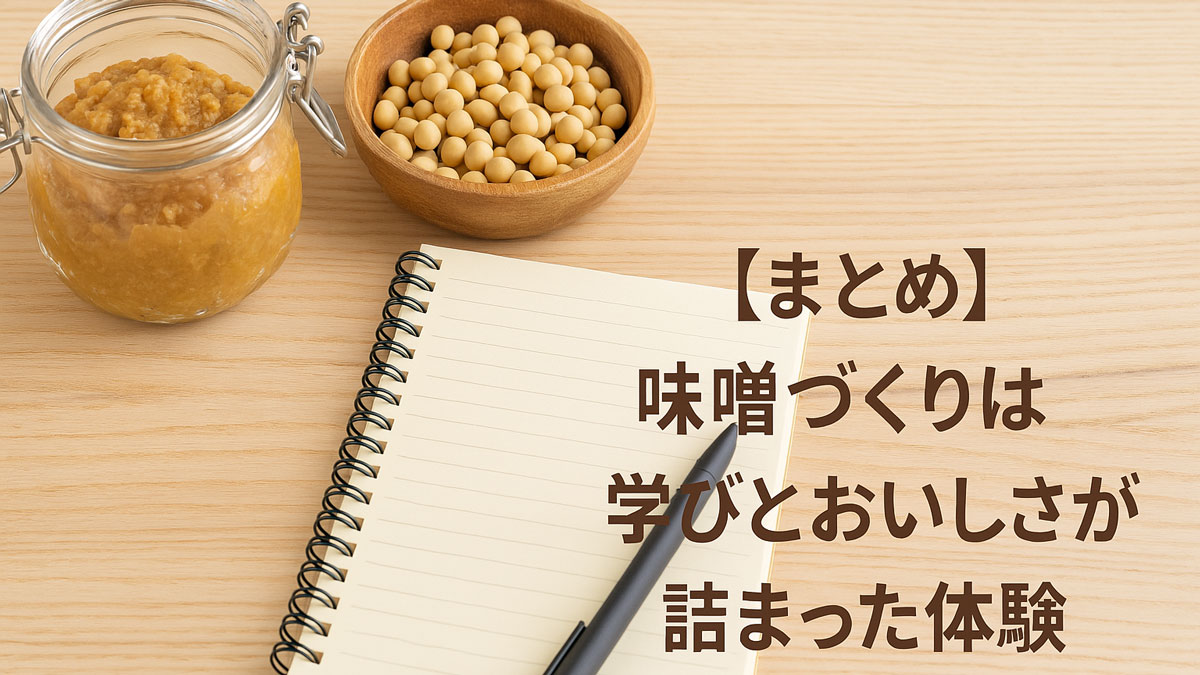
親子で楽しみながら「科学・食・文化」を学べる
味噌づくりを通して子どもが得られる学びは、大きく分けて次の3つに集約できます。
| 学びの要素 | 内容 | 関連する教科・分野 |
|---|---|---|
| 科学的視点 | 発酵、微生物、温度と湿度、観察と記録 | 理科・自由研究 |
| 食育・栄養 | 自分で作ったものを食べる意義、塩分や発酵食品の効果 | 家庭科・生活科 |
| 文化と歴史 | 日本の食文化、地域ごとの味噌の違い、昔の暮らし | 社会・総合学習 |
このように、味噌という日常的な食材の中には、多角的な学びの要素がぎゅっと凝縮されています。特別な道具がなくても始められ、五感を使って体験できるからこそ、幼児から小学生まで幅広い年齢に対応可能です。
また、完成した味噌を家族で食べる瞬間は、何よりのご褒美。自分で作った味噌の味に驚いたり、苦労して作ったからこそ味わい深く感じたりと、「作る」「待つ」「食べる」という一連の経験が、子どもの記憶にしっかりと刻まれます。
おすすめの味噌作りキット・書籍・自由研究ツール
「始めてみたいけれど、何を準備すればいいの?」という方のために、初心者向けにぴったりの味噌づくりキットや参考書籍をご紹介します。
● 手軽に始める!おすすめ味噌づくりキット
| 商品名 | 特徴 | 対象年齢 |
|---|---|---|
| 手作り味噌キット(1kg)|みそソムリエ監修 | 材料すべて入り、道具いらず | 小学生以上向け |
| 生こうじ味噌づくりセット|国産原料使用 | 無添加・保存容器付き | 親子で安心して体験可能 |
| 発酵デザインラボキット | デザイン性が高く自由研究向け | 小学高学年~中学生 |
※2025年4月時点の情報です。各商品は通販サイトや自然食品店などで取り扱いがあります。
● 学びを深めるおすすめ書籍・ワークブック
-
『子どもと学ぶ 発酵のふしぎ』(農文協):小学生向けにやさしく解説
-
『手づくり味噌読本』(地球丸):保護者向けにも役立つ実践ガイド
-
『味噌づくり観察ノート(PDF無料ダウンロード)』:各自治体・学校HPに掲載例あり
● プラスアルファで使えるアイテム
-
100~400倍の顕微鏡(スマホ接続タイプも可):微生物観察に
-
温度計・湿度計:発酵環境の記録用
-
写真プリント機能付きアプリ:変化記録とレポートまとめに便利
準備が整えば、自由研究のテーマとして「発酵観察」「カビの出方比較」「保存環境の違い」など多彩なアプローチが可能です。
【結び】
味噌づくりは、親子で楽しみながら学び・感動・おいしさをすべて体験できる貴重な時間です。家での自由研究ネタとしても、学校の授業と連携させる食育教材としても活用できます。
子どもが「手で作ったものを、待って、食べる」——そのシンプルな営みの中に、未来を育むヒントがたくさん詰まっています。
今年の自由研究、または家族の新しい習慣として、ぜひ味噌づくりを取り入れてみてはいかがでしょうか?
出典・参考文献
-
農林水産省「発酵食品のちから」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/foodindustry/fermentation/index.html -
公益財団法人 日本味噌技術センター「味噌の発酵と微生物」
https://www.miso.or.jp/knowledge/fermentation/ -
農文協『子どもと学ぶ 発酵のふしぎ』
https://www.ruralnet.or.jp/book/b612653.html





